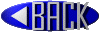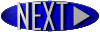焼岳(標高2,455m)は長野・岐阜・富山県境に南北に連なる北アルプスのなかにあって、唯一の歴史上
の噴火記録をもつ活火山である。焼岳は、1915(大正4)年の活動に伴って発生した泥流が穂高岳山麓の梓川
をせき止め、現在の景勝地である上高地の大正池を作ったことで有名であり、現在でも山頂付近から噴煙をあ
げ続けている。焼岳のさらに南には、これ以北の火山に比べて大きな乗鞍岳、御嶽山が続いている。 焼岳は、
その北側の割谷山、南側の白谷山・アカンダナ山(赤棚山)とともに、小火山群をなしている。これらは、槍ヶ岳
〜穂高岳〜乗鞍岳を結ぶ分水嶺上にあり、北北東〜南南西方に配列している。割谷山火山はその原形を
留めていないのに対して、白谷山火山(アカンダナ山を含む)と焼岳火山は火山地形をよく残している。
焼岳火山は成層火山ではあるが、山頂部は溶岩円頂丘状であり、火山帯の基礎は、高いところで1500〜1800m
にまで分布している。これらの火山の基礎岩は、古生代の堆積岩類と中世代白亜紀の火砕岩(濃飛流紋岩)
、これらに貫入する花崗斑岩である。
噴火の残っている記録では、天正13年(1585)、安政5年(1858)、明治40〜45年(1907
〜12)、大正2〜3年(1913〜14)、大正4年(1915)、等で、この後も大正8年、11〜14年、
昭和2年、6年、7年、27年と小噴火があった。 最後の噴火は昭和37年(1962)で中尾峠の焼岳小屋を破壊、
多量の泥流を流し大正池を急速に埋めている。
山頂一帯は登山禁止になっていたが、1991年11月、28年ぶりに登山規制の緩和措置がとられ、山
頂間近の2393mの北峰まで登山が可能になった。とはいえ、噴火活動の状況で再び規制される可能性もある。