|
┗┣藻類の分類
|
藻類の分類
|
藻類とは,光合成で酸素を発生する生物から,陸上植物 (コケ植物・シダ植物・種子植物) を除いたものだ。光合成で酸素を発生する生物には,シアノバクテリアやプロクロロンのように,核をもたない原核生物も含まれる。
- バクテリアに属する藻類
- シアノバクテリア,原核緑藻
- 真核生物に属する藻類 (主に単細胞)
- 灰色藻,ユーグレナ藻,クリプト藻,渦べん毛藻,ハプト藻,クロララクニオン藻
- 真核生物に属する藻類 (単細胞または多細胞)
- 紅藻,不等毛類 (褐藻など),緑色植物 (緑藻など)
|
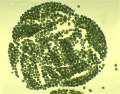 
アオコ (Microcystis)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
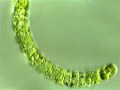 
スピルリナ (Spirulina)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
藍藻,藍色細菌とも呼ばれる。150属2000種が知られている。原核生物である細菌に属し,シアノバクテリア門をつくる。酸素発生型光合成をするが,核をもたない。
先カンブリア時代に大規模なストロマトライトを作った。温泉水の流れ出す場所で深緑色のマットを作る。
光合成色素は,クロロフィルaとフィコビリンである。
|
 
プロクロロン (Prochloron)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
プロクロロンに代表され,原核生物である細菌に属する。
海洋性の群体ホヤと細胞外共生している。
光合成色素は緑色植物と同じ,クロロフィルaとbである。フィコビリンはない。
|
 
シアノフォラ (Cyanophora paradoxia)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
グラウコシスティス (Glaucocystis)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
淡水性の4属で灰色植物門をつくる。
細胞内に2–4個の葉緑体があり,葉緑体の微細構造はシアノバクテリアとよく似ている。シアノバクテリアが共生しているものもあり,シアノバクテリアから葉緑体への進化過程を調べる好材料である。
|
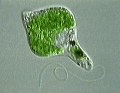 
ミドリムシ (Euglena)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
ペラネマ (Peranema)
従属栄養 (光合成をしない) の捕食生物
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
ミドリムシ藻類ともいう。べん毛で活発に運動するが,葉緑体があり,かつては動物と植物の両方の性質を備えた生物と言われた。40属800種が知られている。
|
 
セラティウム (Ceratium)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
ヤコウチュウ (Noctiluca)
従属栄養 (光合成をしない) の捕食生物
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
2本のべん毛を持つ単細胞生物である。130種,2000種が知られている。光合成をするグループとしないグループがある。
渦をまくように細胞を回転させて泳ぐ。
葉緑体は3重の包膜に包まれている。
|
 
タバコグサ (Desmarestia batacoides)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
スジメ (Costaria costata)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
ナヴィクラ (Navicula)
珪藻に属する
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
褐藻,珪藻などが属する大きなグループである。クロロフィルaとcを持つ,3重のチラコイドを持つなどの共通性から,一つにまとめられた。
同じくクロロフィルaとcを持つクリプト藻類・渦べん毛藻類・ハプト藻類とは,細胞構造が大きく異なる。
|
クロララクニオン藻(Chlorarachniophyceae)
|
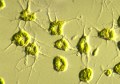 
クロララクニオン (Chlorarachnion)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
クロロフィルaとbを持つので,以前は黄緑藻類に分類されていた。
しかし,包膜が4枚あるので,藻類が細胞内に取り込まれた二次共生生物だとわかる。
|
 
マルバアマノリ (Porphyra suborbiculata)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
ユカリ (Procamium telfaiae)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
キントキ (Prionitis angusta)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
600属5000種が知られている。大部分が海産で潮間帯に生息している。
紅藻類のアマノリは,浅草のりとして知られる。チノリモ類に属するイデユコゴメは,草津温泉 (群馬県) やカムイワッカの滝 (北海道) など,強酸性の温泉に生息している。
胞子で増殖する。
|
 
プリムネシウム (Prymnesium)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
プリューロクリシス (Pleurochrysis)
円石藻に属する
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
クロロフィルaとcをもち,色素としてフコキサンチン,β‐カロチンなどをもつ。70属300種が知られている。
ハプト藻類に属する円石藻は,炭酸カルシウム骨格を作る。
|
 
クリプトモナス (Cryptomonas)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
単細胞で2本のべん毛をもつ。クロロフィルaとcに加え,フィコビリンたんぱく質も持つ。約200種知られている。
もともと葉緑体をもたないべん毛生物が,単細胞の紅藻様生物を取り込んで葉緑体を獲得したのだろう。
|
 
カサノリ (Acetablaria ryukyurnsis)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
ウスバアオノリ (Enteromorpha linza)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
 
クンショウモ (Pediastrum)
(筑波大学生物科学系植物系統分類学研究室)
|
クロロフィルaとbをもつ。
プラシノ藻類,アオサ藻類,トレボウクシア藻類,緑藻類,車軸藻類に分けられる。500属16000種が知られている。
陸上植物の祖先である。
|
|
© 2002 Gifu University, Shin‐Ichi Kawakami, Nao Egawa.
|